

・消防団に入団を考えているけど火災現場では何をするの?
・初めての出動要請が来たけどどうすればいいのかわからない!
消防団は、住んでいる地域で火災が起きた時などに消化活動や交通整理、避難誘導の対応をする団体です。
これから消防団へ入団を考えているという人や、初めて火災現場に行くという人はどんなことをすればいいのかわからないと思います。
特に、話では消防団の活動内容をざっくりと聞いていても、実際に初めて出動するとなると何をすればいいのかわからず慌ててしまうかもしれません!
っというのも、私自身も初めての消化活動では慌ててしまい、何からすればいいのかさっぱりわからなかった一人です。
実際に消防団に入団した私も活動内容は聞いたものの、自分が火災現場に行くなんてまだずっと先の話と思ってあまり意識していませんでした。
そこで今回は、消防団が火災現場でどんなことをするのかを紹介していきたいと思います!
これから消防団への入団を考えている方や、消化活動に行く人は参考にしてみてくださいね。
目次
消防団が火災現場ですることは?
消防団が火災現場ですることは、大きく分けて2つです。
消化活動と消化活動をしている人のサポートになります。
現場に早く到着した団員は、近くの防火水槽からホースをつなげて消化ポンプへの水を送る準備をします。
メインは消防士の方が消化をするという地域もあるようですが、目の前で火災が起きているのに消化しないでいるわけにもいきませんので、消防団も場合によっては前へ出て消化活動をします!
しかし、実際に現場に足を運ぶとそんな状況ではないのが火災現場です。
ここからはどんな現場でも、守りたい流れを紹介していきます。
火災現場ですること①:団の部長の判断を仰ぐ
本業の仕事がある時は必ず出動しているとは限りませんが、まずは団の部長の判断を仰ぎましょう!
部長は毎年交代制で消防団の中に一人存在しているはずです。
火災現場に到着後、部長もきているならまずは部長の判断を待ちます。
各消防団ごとの連絡網を使うなど、実際の火災現場へ出動する前に連絡を取っていると思います。事前に部長が出動できるのか確認しておきましょう!
火災現場ですること②:分団長の指示に従う
火災はいつ何時起こるかわかりません。
日中に起きることもあれば、夜中に突然出動要請がくることもあります。
部長が出動できない時は、消防団の分団長の指示に従いましょう!
分団長は、各分団をまとめる団長ですので直接消化活動をすることはないかもですが、現場の消防団に指示を出してくれます。
イメージでいうと、消防署→分団長→消防団部長という流れで情報が流れてくるのです。
そのため所属している消防団の部長が欠席の場合は、分団長の指示に従いましょう!
火災現場ですること③:先に到着している消防団のサポート
火災現場に行くと、近くの消防団が先に到着していることもあります。
隣の地域の消防団も駆けつけてくれるのが火災現場ではあるので、そんな時は先に到着した消防団のサポートをしましょう。
消防訓練などでお互い顔見知りになっているかと思います。火災の状況を聞いてみるのもこの時がいいと思います。
どうしてもわからないときはベテランの団員に聞こう!
とにかく火災現場ではすごいことになってます。
火災の規模によっては道路が通行止になっていることもあります。
部長や分団長、先に到着した消防団がいない場合はベテランの団員に何からすればいいのか聞きましょう!
無事に鎮火!消化活動終了後は何をするの?
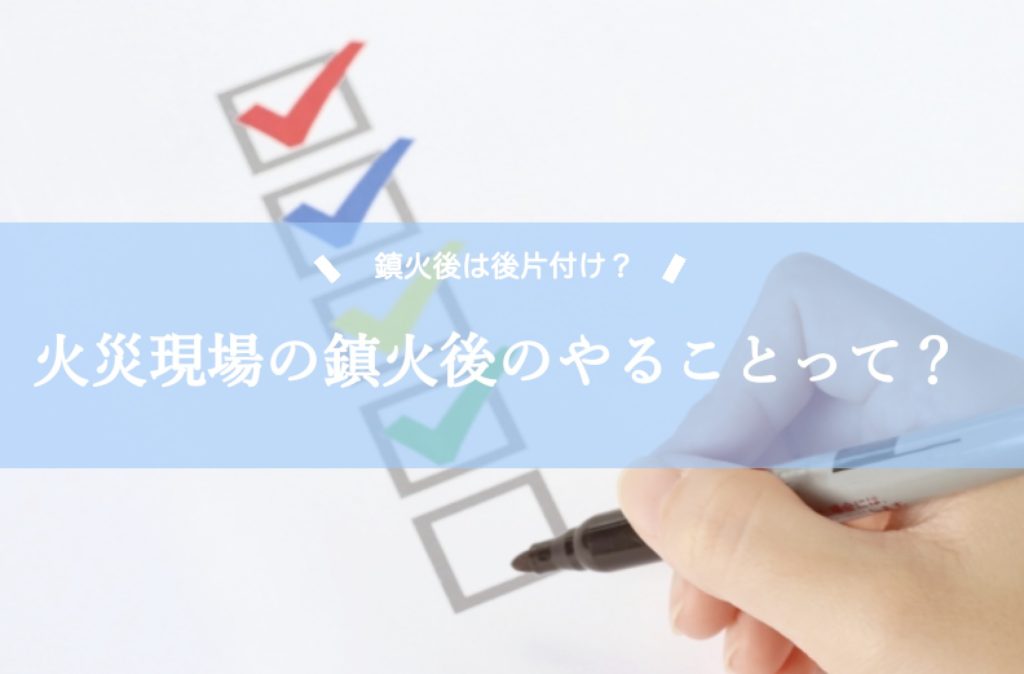
消化活動が終わっても消防団の仕事はあります!
特に建物火災の場合には、出荷元を調べる現場検証や鎮火後に火が出てこないか火の番もしなければいけません。。
消防職員は消化活動のみ完了したら撤収してしまいますので、後片付けや鎮火後の火の番は消防団員が引き受けることになります。
ここからは、鎮火後にすることを紹介していきたいと思います。
鎮火後の火の番をする
消化終了後にすることは、火の番をすることです!
火は鎮火しても、内部に残った熱により煙が出てきて火が出ることもあります。
特に田舎の畳が多い家の場合、畳の内部の熱が時間が経ってから燃え始めることも多く、大きな家の場合には火災鎮火後24時間は火の番をしなければいけないこともあるんだとか!
防火水槽の水の補給
消化活動で使用した防火水槽の水の補給も、消化後にします。
地域のあちこちにある防火水槽は、いつ火災が起きるかわからないので常に満タンにしておかなけれないけないのです。
そのため、各防火水槽へ水を補給していきます。
火の番をしながら各分団のポンプ車とホースと使って順番に水を補給していきます。
消化活動で使ったホースのメンテナンス
消化活動で使ったホースのメンテナンスも、消化終了後に順次していきます。
火災現場で汚れたホースの汚れを洗い流して干して、次回また使える状態にしておくのも消防団の仕事です。
訓練で使うこともある綺麗なホースも、消化活動後には汚れます。
汚れを落としたり、穴が空いてしまったホースの処理などもこの時にしていきます。
消防署ならホースを乾かしてくれる

消防署には上の画像のようにホースを吊るす設備が整っているとのことで、今回初めてホースを乾かさせていただきました。
水道とホースも貸してくれるので、ホースを洗った後に干せるのは羨ましいです。
最後は夜警
火災があったということで、火の番が解除になったら夜警パトロールをすることもあります。
夜警パトロールは本来年末に「カンカン、カンカン」と音を立ててポンプ車で回るのですが、火災が起きた時も注意を促す意味で地域をパトロールします。
夜警をしつつ、最後にもう一度火災現場を確認後、いよいよ消化活動終了となります。
消化は1時間でも出動時間は12時間以上になることも

消防団の消化活動について紹介してきました。
消防団の消化活動は、放水ポンプを使って火災現場に放水することもあれば、消防士のサポートに回ることもあります。
実際の消化活動に1時間くらいだったとした場合でも、その後の後片付けや夜警パトロールなどを含めると出動時間は12時間以上になることもあるのです!
本来は団員全員で出動するべきなのですが、本職の仕事を持っていたりすると全員が出動できないこともあります。
消化活動を終えた団員が、その後の後片付けをしなくてもいいように交代で一連の消化活動をできればいいのですが現実的には難しい地域が多いと思います。
もしもの消化活動では、火の番をする時間や後片付けの時間を含めると12時間以上かかることもあるということを覚えておいてほしいと思います。
合わせて読みたい








![【福島】「楽しくてやめられず」育児休業中に中古車販売で2億円稼いだ税務署職員に懲戒処分 [ぐれ★]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2024/04/スクリーンショット-2024-04-26-20.57.07-300x168.jpg)

![引っ越し作業員に“心づけ”を渡す慣習を知って驚く若者たち「人件費はもう払ってる」「二度と会わない人たちなのに」 [おっさん友の会★]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2024/04/スクリーンショット-2024-04-25-20.44.10-300x200.jpg)
![【栃木2遺体】逮捕の男「大金もらって引き受けた」 報酬目的の可能性 [PARADISE★]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2024/04/スクリーンショット-2024-04-25-20.41.32-300x201.jpg)






![【福島】「楽しくてやめられず」育児休業中に中古車販売で2億円稼いだ税務署職員に懲戒処分 [ぐれ★]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2024/04/スクリーンショット-2024-04-26-20.57.07-150x150.jpg)







![【値上げラッシュ】ヤクルト、10年ぶり値上げ 5本パック216円→259円 原材料高騰で9月から [ぐれ★]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2023/06/4903080988960_1_L-150x150.jpg)


![完璧な結婚相手でもクチャラーで無理 クチャラーって苛つくよな? [194767121]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2024/02/restaurant_rich_couple-300x300.jpg)

![K-POPグループのリーダー、知的障がいを装い兵役逃れか…懲役1年・執行猶予2年を宣告 [朝一から閉店までφ★]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2023/09/idol_man-300x168.jpg)


![【悲報】ビットフライヤー創業者「スイスで魚とワイン一杯頼んだら1万円。日本円よわよわw」 [419087453]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2023/07/money_chingin_kakusa_man.jpg)

![【教育】「英語の時間が足りない」受験生悲鳴─24年共通テストは英語筆記の分量がセンター時代の"1.8倍"…問題量が年々増加 [デビルゾア★]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2024/01/school_test_seifuku_girl-300x288.jpg)
![ダイソー商品、老舗玩具メーカー「うんち無限製造機」に酷似 パクったか?【画像】 [837857943]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2024/01/unchi_character-300x300.jpg)
![「日本の地震は報い」発言の中国アナウンサー “解雇” 仕事失うも800万人のフォロワー得る… 3億1000万人が「いいね」 [煮卵★]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2024/01/jishin_house-300x213.jpg)
![セクシー女優・京野美麗「過去に松本人志から強制猥褻行為を受けた。裁判で協力する」 [501864527]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2024/01/csgHTdN-258x300.jpg)
![松本人志「ワイドナ出ます」 フジテレビ・吉本興業「聞いてないぞ」 [501864527]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2024/01/松本人志-300x267.jpg)
![乙武さん、TENGAを公式からプレゼントされるもそれを動かす右手が無いことで困り果てる [632443795]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2024/01/gVwbhqo-176x300.jpeg)
![タモリみたいな頭のいい人でも認知症になるんだな [837857943]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2024/01/sunglass_normal-300x115.jpg)
![【悲報】炎上した海保機の通信士、任務が終わったら結婚する予定だった😭 [323057825]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2024/01/airplane-300x195.jpg)
![マドンナ(65)に「お婆ちゃんもうやめて、見てて恥ずかしい」の声殺到 [632443795]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2024/01/tlyJryA-188x300.jpeg)
![【能登地震】千羽鶴は被災地に送るべきではない?…「千羽鶴送付を禁止する法律を」との声も [おっさん友の会★]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2024/01/origami_senbaduru-234x300.jpg)
![ほらかけるぞ!1、2、3!スーパーマーケットで30代女性に尿をかけた安田一二三容疑者逮捕 栃木 [866556825]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2023/11/job_chinretsu_woman-300x294.jpg)
![私人逮捕系youtuber煉獄コロアキ チャンネル削除→月200万の不労所得が無くなった!と逆上www [509689741]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2023/11/迷惑youtubere-300x300.jpg)
![「日本円の紙くず化は最終ステージに突入」 プレジデントオンライン [128776494]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2023/10/money_weak_yen-300x283.jpg)
![女性「生理用品買うとき毎回複雑な気分になる。ハート柄、ピンク…限定的な女性像の押しつけはやめて」 [244661201]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2023/11/UzhCxQt-235x300.jpg)
![亀田製菓「柿の種にピーナッツが混入したので回収します」 [866556825]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2023/11/APkffXd-227x300.jpg)
![【闇深】櫻井翔もジャニーズ退社へ。キムタク以外全員退社する流れ [801948679]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2023/11/XrfBvhk-300x219.jpg)
![電話に出られないから会社辞めます 20代の7割以上が苦手、言葉が出ず泣き出す人も…対策と電話の必要性 [ばーど★]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2023/11/電話苦手-300x165.jpg)
![高齢男性、電車で泣く赤ちゃんに激高 親に「人間失格」と暴言 制止されるも「甘やかすから日本が駄目になる」…警察に引き渡される [ばーど★]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2023/11/老害-256x300.jpeg)
![97歳運転の車がビルに突っ込む 「車に乗っていなかった」などと意味不明な説明 [135853815]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2023/11/高齢者自己-300x132.jpg)

![【群馬】フィットネスジムの天井裏に侵入しシャワー中の女性の裸をのぞき見か 高校教諭の男を逮捕 [シャチ★]](https://namasanroom.com/wp-content/uploads/2023/11/TrDWNJF-178x300.jpg)











































